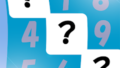「日本はDXで世界に遅れをとっている」という論調の記事を多く見かけますが、多くの人には聞きなれない言葉ではないでしょうか。
それは、政府のDXが、企業の競争力維持を最優先にしているため、街の人には聞こえてこないんです。経済がダメになっては国民の生活どころではないという考えですね。
2018年には、経済産業省から「DX推進のためのガイドライン」が発行されており、『各企業は、競争力維持・強化のために、デジタルトランスフォーメーション(DX:DigitalTransformation)をスピーディーに進めていくこと』とされています。
つまり、諸外国との競争力を失う前に対策せよとのことなのですが、特に中小企業においては、どうしろというのかという空気感があります。
DXとは
DXの解釈には諸説ありますが、「第4次産業革命」と表現されることもあります。過去の産業革命は以下となります。
- 第一次産業革命 ・・・ 蒸気機関による「機械化」
- 第二次産業革命 ・・・ 工場による「大量生産化」
- 第三次産業革命 ・・・ コンピュータによる「自動化」
- 第四次産業革命 ・・・ モノのインターネットによる「産業構造改革」(ICT革命/進行中)
第四次産業革命は、進行中のため最終形は不明ですが、究極には、世の中の文房具やら日用品やら、すべての「モノ」の状態がインターネットを通して収集され、社会にとって最適な「モノ」の状態の組み合わせをAIが決定し、再設定する仕組みを目指すはずです。
Aパターンの時のアクションプランはNo.1、Bパターンの時のアクションプランはNo.2という感じで、人ではなく、AIが決定します。
会社業務では、個人の経験により培われた業務ノウハウが、担当の引継ぎにより劣化、欠落するという問題がありますが、それもデジタル化とAIの組み合わせにより解決されます。(あくまで理想)
個人の勘や感情により非論理的な判断をすることもなく、不適切会計などということもなくなります。これは、ため込んだ知識や、ノウハウの提供を意義としていた部門は不要になるということです。そして、AIの判断は、蓄積した情報量が多いほど正しい結果となり、同じことを生業とするならば、より多くの関連情報をデジタル化して蓄積できている企業が有利になるため、早く着手しなければならないのです。
2025年の崖
国内のDX推進の脅し文句となっているのが、「2025年の崖」というキーワードです。「DX推進のためのガイドライン」によると、古いシステムは2025年になると競争力を失うという推測になっています。
簡単に言うと、2025年までには、様々な情報基盤が刷新され、古いシステムは、新しいクラウドサービスが利用できず、同業他社(特に海外企業)に対しての競争力を失うということです。
乗り越え方は、3パターン程度に分類されて検討されています。
ただ、「企業ごとの特性に応じた形でシステムを刷新しろ」と言われているのですが、それで良いのでしょうか。未来の情報基盤をどのように想定するのかについて、政府の方針が必要だと考えているのですが、具体的な方針はありません。皮肉なことに、政府の意思決定プロセスが古く、正解がない問題に対しては、意思決定できないのかもしれません。
これからは、誰もが正解がない問題に取り組まなければならない時代と言われています。
政府のDX
従って、まずは政府のDXが必要でしょう。ハンコとかFAXから始まりましたね。
持論ですが、DXとは交通や電気、水道などのライフライン、その他の公共インフラに適用しなければ、社会の役に立たず意味がないと考えています。
各企業が必要なデジタル情報を、各々で整備させるのではなく、政府として、交通、ライフライン、公共インフラについての将来の管理方針を決定し、それに企業のビジネス情報、個人の生活情報を加えた全体のフォーマットぐらいは策定して提示しなければならないでしょう。全てを統合的に扱うのが合理的ですから。そして定期的に見直しができるルールも必要です。
内閣府が運営するRESASが例になるかと思うのですが、微妙にバラバラなものが出来上がってます。データは有用なのですが、プログラムから扱いにくく、二次利用するのに手間がかかるのです。
日常生活のDX
企業向けの話題と感じた人もいると思いますが、今の生活を振り返ってみると、電源設備、給湯設備、エアコン、テレビ、時計、電球、オーディオ機器、スマートフォンなど、多くの「モノ」がインターネットに繋がり、自動で調整が行われたり、家庭や個人に合わせた設定や、購入品の提案を受けてはいないでしょうか。
いつの間にか、起床や就寝などの生活リズム、食べたもの、趣味趣向などの情報を提供していて、精度は置いといて、行動予測やニーズの分析結果を受け取っているのです。
実は、「日常のDX」は「企業のDX」より進んでいると言え、生活の中でも、購買分野では、Amazon、Uber、Netflix、Google、Appleといった企業への依存度は高いと思われます。
また、決済分野では、電子マネーでの決済が一般化してきた感じがします。これまでは、Amazonでの購入品リストはAmazonが独占できたわけですが、電子マネーの運営会社は、どこの買い物であっても、個人に紐づいた購入品リストを入手できるため、様々な会社がこぞって電子マネーの仕組みを提供し始めたわけです。
多くの人が、「電子マネー決済で享受する付加価値」が、「提供情報(購買リスト)の価値」を上回ったと感じているため、一般的になったものと推測されます。
この他にも、ずいぶん手軽に投資ができるようになりましたね。本人認証に問題なければ、口座開設からエントリーまで3日かかりませんね。
ビジネスチャンス
変革の時期はチャンスの時期です。
例えるなら、Windowsが発売された時代や、インターネットが始まった時代のような、可能性に満ちたエキサイティングな時代だと感じています。いままでは技術的な問題から実現できず、想像すらしなかった形のビジネスが次々と生まれてくるのではないでしょうか。
そのチャンスはアイディアによって得るもので、大企業だからできることではなく、個人でも可能なものです。企業が手に入れられる情報も、個人が手に入れられる情報も、技術的には同じものが入手可能で、それをどのように組合わせて利用するかが重要なのです。
また、チャンスとは資産を手に入れることとは限りません。社会に貢献するチャンスでもあります。ちょっと哲学ですが、充実感とは社会に貢献することで得られるものです。
デジタル社会の到来は避けることはできません。
ならば、「やさしく温かなデジタル社会」について、一緒に考えていきましょう。